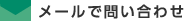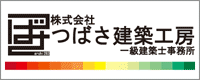児童手当
更新日:2025年5月7日
注:令和6年10月からは、児童手当制度が改正されました。制度改正に伴う手続などは令和6年10月からの児童手当制度改正についてをご覧ください。
支払通知ハガキの廃止について
令和5年度まで送付していた児童手当の年間支払予定額を記載したハガキの送付について、令和6年度からは廃止されます。
児童手当の金額改定時には従来どおり額改定通知が送付されますので、当該通知をもって支給月額を確認してください。
通帳に記帳した場合は「タテバヤシシジドウテアテ」と印字されます。
制度の目的
児童手当により、家庭などにおける生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
支給対象
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童が支給対象となります。また、父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度が高いかた(恒常的に所得が高いかたなど)が受給者となります。
注:児童が海外にお住まいの場合は、単身留学を除き、原則手当は支給されません
注:離婚協議中などにより父母が別居している場合は、児童と同居しているかたに手当を支給します(単身赴任を除く)
注:児童が児童養護施設などに入所している場合は、施設の設置者などが受給者となります
注:公務員のかたは、勤務先での支給になります
支給金額(児童1人当たりの月額)
| 区分 | 支給月額 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 第1・2子 | 月額 15,000 円 |
| 第3子以降 | 月額 30,000 円 | |
| 3歳以上高校生以下 | 第1・2子 | 月額 10,000 円 |
| 第3子以降 | 月額 30,000 円 |
注:22歳になった後、最初の3月31日を過ぎると、児童手当制度上は児童の数に数えません。また、18歳年度末到達後から22歳年度末までの児童については、経済的な負担のある児童を数えます
支給時期
偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)のそれぞれ10日に、前月分までの手当を支給
注:10日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります
所得制限及び所得上限について
令和6年10月分の手当(令和6年12月定期払)から、所得制限及び所得上限は撤廃となります。
注:父母のうち、生計を維持する程度の高いかた(恒常的に所得の高いかたなど)が受給者となる原則は変わりません。
注:所得上限限度額超過のため、現在児童手当の受給資格が喪失となっているかたは、児童手当を受給するためには改めて申請(認定請求)が必要です。こちらを確認のうえ、早めに申請してください
所得制限・所得上限限度額表(令和6年9月まで)
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
| 0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,700,000円 |
| 1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
| 2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
| 3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
| 4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
| 5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
注:扶養親族が5人を超える場合は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を所得制限限度額に加算します
申請手続き
児童手当を受給するためには、認定請求書の提出が必要です。出生、転入などで受給資格が生じたときは、子育て支援課子育て支援係へ申請(認定請求)してください。
注:公務員のかたは、勤務先で申請手続きを行います
注:児童手当は、申請をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請が遅れた場合、さかのぼって受給することはできません
注:出生の場合は出生した日から、転入の場合は前住所地の転出予定日から15日以内の請求であれば、月をまたがっても、出生した月や転出した月の翌月分から支給されます。15日を過ぎると、手当が支給されない期間が生じますのでご注意ください。
申請に必要な物
- 個人番号(マイナンバー)カード、通知カード又は個人番号記載の住民票(申請者及び配偶者分)
注:氏名・住所変更などがあったかたで裏面に現在の氏名・住所の記載が無い場合は、個人番号通知カードでの受付はできません - 申請者名義の預金通帳
- 身分証明書
- 【仕事の都合などで児童と別居する場合】
児童の個人番号(マイナンバー)カード、通知カード又は個人番号記載の住民票
注:氏名・住所変更などがあったかたで裏面に現在の氏名・住所の記載が無い場合は、個人番号通知カードでの受付はできません - 【3歳未満の児童を養育しているかたで、国家公務員共済組合(日本郵政共済組合など)又は地方公務員共済組合の組合員の場合】
申請者本人の健康保険証の写し
注:健康保険証のコピーを取る際は、記号、番号、保険者番号及び二次元コードの部分にマスキング(黒塗りなど)を施してください - 【18歳年度末から22歳年度末までの児童を養育しており、その児童を含めると第3子以降となる児童がいる場合】
18歳年度末から22歳年度末までの児童の個人番号(マイナンバー)カード、通知カード又は個人番号記載の住民票
注:氏名・住所変更などがあったかたで裏面に現在の氏名・住所の記載が無い場合は、個人番号通知カードでの受付はできません
注:離婚協議中などにより父母が別居している場合は、離婚協議中であることの申立書及び申立の事実を証明する書類が必要です
注:この他、必要に応じて提出する書類があります
児童手当の振込口座に公金受取口座を指定できるようになりました
令和4年10月より、マイナポータル上で公金受取口座を登録しているかたについては、児童手当の振込口座に公金受取口座を指定することができるようになりました。本市で新しく児童手当を受給するかたは、申請時に公金受取口座を希望するとして届け出てください。本市で児童手当を既に受給しているかたで、公金受取口座への振込を希望する場合は、窓口にて金融機関変更届をご提出ください。
注:公金受取口座を登録している場合でも、児童手当の金融機関変更届の提出がない場合は、児童手当は公金受取口座に振り込まれません
注:公金受取口座を変更した場合にも、公金受取口座を希望している場合は自動的に児童手当の振込口座が変更となります。ただし、時期によっては変更前の口座に振込となる場合がありますので、ご了承ください
注:公金受取口座を使うのをやめた場合は、窓口で金融機関変更届を提出のうえ、その旨をお伝えください
現況届について(令和4年6月より原則不要となりました)
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件(子どもの監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
令和4年6月(令和4年度児童手当・特例給付現況届)より、以下に該当する場合を除き、現況届の提出が不要になりました。
引き続き現況届の提出が必要なかた
- 児童と別居している(住民票上の住所が異なる)かた
- 受給者からみた児童の続柄が「子」でないかた(「妻の子」や「子の子」など)
- 離婚協議中につき配偶者と別居していることを理由として児童手当を受給しているかた
- 配偶者からの暴力などにより、住民票上の住所が実際の居住地と異なるかた
- 支給要件児童の戸籍が無いかた
- 施設設置者等(里親など)
- その他市が必要と認めたもの
対象者には毎年6月上旬に現況届用紙を送付しますので、手続きをしてください。
現況届の提出が必要なかたは、現況届を提出しないと手当が受けられなくなりますので、必ず手続きをしてください。
国家公務員共済組合(日本郵政共済組合など)又は地方公務員共済組合の組合員のかた
- 受給者本人の健康保険証の写し(表面)
注:お子さんの保険証ではありません
注:コピーを取る際は、記号や番号、保険者番号及び二次元コードの部分にマスキング(黒塗りなど)を施してください
現況届用紙のほかに、申立書が同封されているかた
- 同封の申立書(記入の上、提出してください)
例:別居監護申立書、監護・生計維持申立書、児童手当などの受給資格に係る申立書など
その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
こんなときは早めに届出を
以下のようなときは、届け出てください。届出を行わないと、手当が受給できない月が生じたり、返金していただいたりすることがあります。
他の市区町村に転出するとき
他の市区町村に住所が変わる場合は、手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村役場で、新たに申請をしてください。
受給者又は児童が国外転出するとき
受給者又は児童の住所が日本になくなると、原則として手当の受給資格が消滅します。さかのぼって国外転出となった場合は、手当を返還していただく場合もあります。
児童が増えたとき
既に児童手当を受給しているかたが、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、申請(額改定認定請求)が必要です。
児童と別居することになったとき
受給者の仕事の関係、児童の学校の関係などで、児童と受給者の住所が別々になったときには、「別居監護の申立書(児童が市外在住の場合は児童の個人番号の記載が必要になります)」を提出してください。
児童を養育しなくなったとき(児童が施設入所したときを含む)
子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき
公務員のかたは、児童手当が勤務先から支給されますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
受給者が同じ市区町村内で住所が変わったとき
「氏名・住所変更届」を提出してください。
配偶者の住所が変わったとき
「氏名・住所変更届」を提出してください。
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名・住所変更届」を提出してください。
振込先の金融機関口座を変えるとき
「口座変更届」を提出してください。振込前月の10日までに変更届を提出すると、次回の振込から変更可能です。
例:2月10日の振込から口座を変更したい場合は、1月10日までに変更届を提出してください
注:受給者名義の口座に限られます
受給者が加入する年金が変わったとき(令和4年6月から)
「氏名・住所変更届」を提出してください。
注:3歳未満の児童を養育しているかたで、国家公務員共済組合(日本郵政共済組合など)又は地方公務員共済組合の組合員の場合は申請者本人の健康保険証の写しが必要です
注:健康保険証のコピーを取る際は、記号や番号、保険者番号及び二次元コードの部分にマスキング(黒塗りなど)を施してください
受給者が婚姻又は離婚をしたとき
引き続き児童手当を受給する場合は「氏名・住所等変更届」を、新たに配偶者が児童手当を受給する場合は「受給事由消滅届」及び「認定請求書」を提出してください。
注:婚姻した場合は、現在の受給者より配偶者のほうが所得が高く、配偶者と対象児童との間に養子縁組の意思があれば、配偶者が新しい受給者となります。
注:受給者が婚姻した場合は、配偶者の個人番号(マイナンバー)カード、通知カード又は個人番号記載の住民票が必要です(氏名・住所変更があったかたで、裏面に現在の氏名・住所の記載が無い場合は、個人番号通知カードでの受付はできません)
注:新たに配偶者が児童手当を受給する場合は、配偶者名義の預金通帳が必要です
第3子以降分の手当を月額3万円として受給しているかたについて
児童手当は、令和6年10月の制度改正により、本人の届出に基づき、経済的な負担のある22歳年度末までの児童を数え、第3子以降分の手当を月額3万円として支給することとなりました。
これに際し、経済的な負担を判断するため、以下の場合には手続が必要となります。
- 末子以外の児童が18歳年度末を迎えるとき
- 18歳年度末以降22歳年度末までの児童が短大・専門学校を卒業するとき
なお、児童の就学・就労の状況等に応じ、該当児童に対する経済的な負担の状況を現況届時に届け出ていただくこととなります。
注:手続時に届け出ていただいた児童の状況から変更が生じる場合(児童の住所変更、児童が学生でなくなる、卒業年月が変わる、児童に対する経済的な負担がなくなる等)は別途届出が必要となります。
注:令和6年10月以降、制度拡充時に届け出ていただいた児童の状況から変更がある場合も、別途届出が必要となります。