子どもの予防接種
更新日:2025年4月24日
令和6年度の麻しん風しん混合ワクチン出荷量減少に伴い、ワクチンの供給が不安定です。
また、令和6年度に定期接種の対象となったかたは、接種期限が変更となりました。詳しくは麻しん風しんワクチン接種期限延長のお知らせをご覧ください。
子どもの予防接種
定期予防接種について
- ロタウイルス
- B型肝炎
- 小児用肺炎球菌
- 五種混合(DPT-IPV-Hib)
- 四種混合(DPT-IPV)
- ヒブ
- BCG
- 麻しん・風しん混合(MR)
- 水痘(水ぼうそう)
- 日本脳炎
- 二種混合(DT)
- 子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染症:HPV)
| 予防接種の種類 | 対象年齢 |
|---|---|
| ロタウイルス | ロタリックス(1価)出生6週0日後から24週0日後までの間にあるもの、ロタテック(5価)出生6週0日後から32週0日後までの間にあるもの |
| B型肝炎 | 生後2か月から1歳になる前日まで |
| ヒブ・小児用肺炎球菌 | 生後2か月から5歳になる前日まで |
| 四種混合・五種混合 | 生後2か月から7歳6か月になる前日まで |
| BCG | 生後5か月から1歳になる前日まで |
| 麻しん風しん混合(第1期) | 1歳から2歳になる前日まで 注:定期接種の他に特例措置対象者がいます。詳しくは、麻しん風しん混合ワクチン接種機関の延長についてをご覧ください。 |
| 麻しん風しん混合(第2期) | 年長児 注:定期接種の他に特例措置対象者がいます。詳しくは、麻しん風しん混合ワクチン接種機関の延長についてをご覧ください。 |
| 水痘(水ぼうそう) | 1歳から3歳になる前日まで |
| 二種混合(ジフテリア・破傷風)ワクチン | 11歳から13歳になる前日まで |
| 子宮頸がん予防ワクチン | 小学6年生から高校1年生相当年齢の女子 注:定期接種の他に特例措置対象者がいます。詳しくは、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)をご覧ください。 |
| 日本脳炎(第1期) | 3歳から7歳6か月になる前日まで |
| 日本脳炎(第2期) | 9歳から13歳になる前日まで |
| 日本脳炎(特例措置) | 平成19年4月1日までに生まれた20歳未満のかたで、4回接種未完了者 |
ロタウイルス
ロタウイルスとは、嘔気・嘔吐と下痢を主症状とする急性胃腸炎の原因となるウイルスです。乳幼児に多くおこり、5歳までにほとんどの子どもが感染すると言われています。
感染すると2から4日の潜伏期間を経て嘔吐、水のような下痢を繰り返すのが特徴的です。重症になると脱水症状、けいれんや脳症などの合併症を起こし入院することがあります。
対象年齢
- 1価ワクチン(ロタリックス):生後6週から24週になる前日まで
- 5価ワクチン(ロタテック):生後6週から32週になる前日まで
注:いずれも初回接種(1回目)は、生後14週6日までに受けてください
接種方法
- ロタリックス(1価ワクチン)の場合:1回目(生後6週から生後14週6日)の接種から4週間あけて、2回目を接種して終了
- ロタテック(5価ワクチン)の場合:1回目(生後6週から14週6日)、2回目、3回目をそれぞれの間隔を4週間あけて接種
注:接種間隔は、接種日を0日として週数を数えます
注:ワクチンの種類は、医療機関ごとに異なりますが、両方とも経口接種です
標準的な接種期間の開始時期
生後2か月
接種場所
B型肝炎
B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気です。一過性の感染で回復する場合と、感染が長く続く場合(キャリアといいます)があります。キャリアになると慢性肝炎になることがあり、さらに肝硬変や肝がんを引き起こす場合があります。予防のためには免疫が得やすい0歳でワクチン接種を行うことが重要です。
注:2か月になったら早めに接種を始めましょう
対象年齢
1歳になる前日まで
接種方法
3回:27日以上の間隔で2回終了後、1回目の注射から139日以上あけて追加1回
標準的な接種期間
生後2か月から9か月に達するまでの期間
接種場所
小児用肺炎球菌
肺炎球菌感染症は、肺炎球菌という細菌によって起こる感染症です。ほとんどが5歳未満で発症します。感染すると、髄膜炎、肺炎、中耳炎などを引き起こします。ワクチン接種により肺炎球菌の感染の予防と、重症化を防ぐ効果があります。
注:2か月になったら早めに接種を始めましょう
対象年齢
生後2か月から5歳になる前日まで
接種方法
- 初回:27日以上の間隔で3回
- 追加:初回3回終了後、60日以上あけて1回 (1歳以降)
標準的な接種期間
- 初回:1歳までに27日以上の間隔で3回
- 追加:初回3回終了後、60日以上の間隔をあけて1歳から1歳3か月の間に1回
接種場所
五種混合(DPT-IPV-Hib)令和6年4月1日から開始
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブの5種混合ワクチンです。
令和6年4月1日から接種が可能となります。四種混合ワクチンおよびヒブワクチンで接種を開始しているかたは引き続き、同じワクチンで接種を進めてください。
ジフテリアは、ジフテリア菌によって起こる感染症で風邪に似た症状や神経まひ、呼吸困難などを引き起こします。
百日せきは、百日せき菌による感染症で長期間続くせきが特徴で、呼吸困難などを引き起こします。
破傷風は、土の中にいる菌が傷口から体内に入り、手足のしびれやけいれんなどを引き起こします。
ポリオは、ポリオウイルスによる感染症で手足のまひを行き起こすことがあり「小児まひ」と呼ばれます。
ヒブ感染症は、インフルエンザ菌b型(Hib)という細菌によって起こる感染症です。口や鼻から細菌を吸い込むことで感染します。
対象年齢
生後2か月から7歳6か月になる前日まで
接種方法
- 第1期初回:20日以上の間隔で3回
- 第1期追加:初回3回終了後、6か月以上あけて1回
標準的な接種期間
- 第1期初回:生後2か月から12か月に達するまでの期間に20日から56日の間隔で3回
- 第1期追加:初回3回終了後、6か月から18か月の間隔をあけて1回
接種場所
四種混合(DPT‐IPV)
ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオの4種混合ワクチンです。
ジフテリアは、ジフテリア菌によって起こる感染症で風邪に似た症状や神経まひ、呼吸困難などを引き起こします。
百日せきは、百日せき菌による感染症で長期間続くせきが特徴で、呼吸困難などを引き起こします。
破傷風は、土の中にいる菌が傷口から体内に入り、手足のしびれやけいれんなどを引き起こします。
ポリオは、ポリオウイルスによる感染症で手足のまひを行き起こすことがあり「小児まひ」と呼ばれます。
四種混合ワクチンの接種によりこれらの感染予防と重症化を防ぐ効果があります。
対象年齢
生後2か月から7歳6か月になる前日まで
接種方法
- 第1期初回:20日以上の間隔で3回
- 第1期追加:初回3回終了後、6か月以上あけて1回
標準的な接種期間
- 第1期初回:生後2か月から12か月に達するまでの期間に20日から56日の間隔で3回
- 第1期追加:初回3回終了後、12か月から18か月の間隔をあけて1回
接種場所
ヒブ
ヒブ感染症は、インフルエンザ菌b型(Hib)という細菌によって起こる感染症です。口や鼻から細菌を吸い込むことで感染します。感染すると、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などのほか、髄膜炎、敗血症、肺炎などの重い病気を引き起こすことがあります。ワクチン接種によりヒブ感染症の予防と重症化を防ぐ効果があります。
注:2か月になったら早めに接種を始めましょう
対象年齢
生後2か月から5歳になる前日まで
接種方法
- 初回:27日(医師が認めるときは20日)以上の間隔で3回
- 追加:初回3回終了後、7か月以上あけて1回
標準的な接種期間
- 初回:27日(医師が認めるときは20日)から56日の間隔で3回
- 追加:初回3回終了後、7か月から13か月の間隔をあけて1回
接種場所
BCG
結核は、結核菌によって起こる感染症です。赤ちゃんは、結核に対する抵抗力(免疫)をお母さんからおなかの中でもらうことができないうえ、乳幼児が発症すると全身性の結核症や結核性髄膜炎になることもあります。ワクチン接種により結核菌の感染の予防と、重症化を防ぐことが重要です。
対象年齢
1歳になる前日まで
接種方法
1回
標準的な接種期間
生後5か月から8か月に達するまでの期間
接種場所
麻しん風しん混合
麻しんは、麻しんウイルスの感染によって起こる感染症です。高熱と発疹が主な症状で感染力が強く、まれに重篤な症状を引き起こすことがあります。
風しんは、風しんウイルスによって起こる病気です。発疹、発熱、リンパ節の腫れが主な症状です。
ワクチン接種により、麻しん、風しんの感染の予防と、重症化を防ぐ効果があります。
対象年齢
- 第1期:1歳から2歳になる前日まで
- 第2期:5歳以上7歳未満で、小学校就学前1年間(年長児相当)
注:年長児となった4月に予診票を郵送します
接種方法
- 第1期:1回
- 第2期:1回
標準的な接種期間
- 第1期:1歳になったら早めに接種
- 第2期:年長になったら早めに接種
接種場所
水痘(水ぼうそう)
水痘(水ぼうそう)は水痘ウイルスによって起こる感染症です。感染力が強く、かゆみを伴う特徴的な発疹が主症状です。水痘ワクチンを1回接種することで重症化を防ぎ、2回接種することで発症を予防することができます。
注:1歳になったらなるべく早くに接種しましょう
対象年齢
1歳から3歳になる前日まで
接種方法
3か月以上の間隔をあけて2回
標準的な接種期間
1歳から1歳3か月に達するまでの間に1回、1回目終了後、6か月から1年の間隔をあけて2回目を接種
接種場所
日本脳炎
日本脳炎は、日本脳炎ウイルスによって起こる感染症です。ウイルスを持つ蚊に刺されることによって感染します。発熱、頭痛、嘔吐などが主な症状です。ワクチン接種により日本脳炎の感染の予防と、重症化を防ぐ効果があります。
日本脳炎ワクチンについて
日本脳炎ワクチンの供給量及び出荷量が不安定なため、医療機関での接種予約が取りにくくなっております。
接種前に、必ず医療機関へお問い合わせください。接種期限到達までに余裕があるお子さんは、供給量が安定するまで、接種をお待ちいただく場合もあります。
なお、第1期初回(1回目・2回目)接種、定期接種として受けられる年齢の上限が近づいているお子さん等を優先に接種できるような対応が取られています。
対象年齢
- 第1期:生後6か月から7歳6か月になる前日まで
注:3歳未満で接種する場合は接種量が異なります - 第2期:9歳から13歳になる前日まで
注:9歳の誕生日の翌月に予診票を郵送します
接種方法
- 第1期初回:6日以上の間隔で2回
- 第1期追加:初回2回終了後、6か月以上あけて1回
- 第2期:1回
標準的な接種期間
第1期:初回を3歳から4歳に達するまでの期間に6日から28日の間隔で2回接種
その後、おおむね1年後に第1期追加を1回接種
第2期:9歳から10歳に達するまでの期間に1回接種
特例措置
平成19年4月1日以前の生まれのかたは20歳未満まで、未接種分が特例措置で接種可能となります。詳しくは健康推進課(保健センター内)までお問い合わせください。
接種場所
二種混合(DT)
ジフテリア・破傷風の二種混合ワクチンです。乳幼児期に受けた三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)または四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)で得られた免疫を強化し、確実な免疫をつけることを目的としています。
対象年齢
11歳以上13歳になる前日まで
注:11歳の誕生日の翌月に予診票を郵送します
接種方法
第2期:1回
標準的な接種期間
11歳に達した時から12歳に達するまでの期間
接種場所
予防接種の受け方
接種費用
無料(予防接種法で定められている接種期間内に接種した場合)
持ちもの
- 母子健康手帳
- 予診票(名前シールを貼り、事前に記入して持参しましょう)
- マイナンバーカード(マイナ保険証)又は健康保険証
接種場所
- 館林市邑楽郡内の予防接種実施医療機関
乳幼児個別予防接種実施医療機関一覧表
注:市外・県外の医療機関を希望されるかたは、事前に手続きが必要な場合があります。事前の申請をおこなわずに接種を受けた場合、全額自己負担となりますので事前に健康推進課へお問い合わせください
予防接種を受けるにあたり共通事項
注意事項
- 事前に予防接種実施医療機関に電話等で予約をして接種してください
- 予防接種には、保護者のかたが同伴してください。保護者以外のかたが連れて行く場合は、予診票裏面の委任状の記入が必要です
- 外国人のかたで日本語が話せない場合は、必ず、保護者のほかに日本語が話せるかたが同伴してください
予防接種を受けることができない人
- 明らかに発熱(通常37.5℃以上)をしている人
- 重い急性疾患にかかっていることが明らかな人
- その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分でアナフィラキシー(30分以内におこるひどいアレルギー反応)をおこしたことがある人
- BCG接種の場合においては、外傷などによるケロイドが認められる人
- その他、医師が不適当な状態と判断した人
予防接種を受けた後の注意
- 接種後30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。急な副反応がこの間におこることがまれにあります
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間の間は副反応が出ることがあります。お子さんの体調に注意しましょう
- 入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう
- 当日は、はげしい運動は避けましょう
- 接種後、体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう
予防接種の副反応
予防接種後に、発熱、接種した部位の発赤、腫れ、しこりなどが高い頻度で認められます。通常、数日以内
に自然に治るので心配の必要はありません。
ただし、接種局所のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状があった場合は、医師の診察を受けてください。
ワクチンの種類によっては、極めてまれに重い副反応が生じることもあります。このような場合に、厚生労働
大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の
給付の対象となります。
長期療養により定期予防接種を受かられなかったかたへの特例措置
定期予防接種の対象であった間に、長期療養を必要とする病気にかかったなどの特別な事情により、予防接種
を受けることができなかったと認められる場合、特別な事情がなくなってから、2年間は定期予防接種として
接種できる場合があります。
注:ただし、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳、五種混合・四種混合は15歳までの年齢制限があります。
事前に申請が必要なため、詳しくはお問い合わせください
特別な事情とは
- 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと
疾病の例はこちら - 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
- 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの
周辺案内図
地図はドラッグ操作でスクロールします。

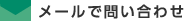
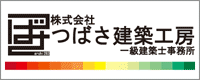

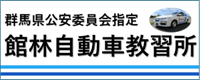
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。