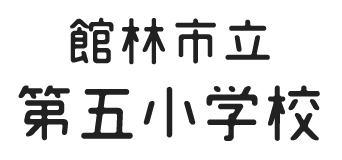上三林のささら舞い
更新日:2021年3月24日
「ささら」の語源は竹で作られた「すりざさら」がさらさらと音を出したことから、ささらの名が生まれたと言われます。
芸能としてのささらは、かつて楽器としてのささらによって獅子が踊ったことから、獅子舞を指すようになりました。ささらは、農耕社会の祭で五穀豊穣(ごこくほうじょう)のきがん・感謝・やくばらいなどのために、地域を上げて行われます。
平成5年(1993年)、に市の重要無形民俗文化財に指定されました。
市内では、上三林、木戸、羽附旭町などで現在でも演じられています。
(この文章は「館林かるた」の読み札に書いてあるものを簡単に直してつくりました。)

獅子舞にはちゃんとストーリーがあることを知り、ビックリ。
2ひきのオスが1匹のメスをめぐって争うというお話だそうです
これだけの格好をしているにもかかわらず
素早く動いていたのにはさらにビックリ。拍手です。
棒術です。柳生新陰流と言っていましたが、
本当に、剣術の練習をしているように見えました。
もしかして、この踊り、実は徳川幕府に反抗する力を
なくさないための戦闘訓練だったのでは?と思いました。
ちなみに、一番上級の技は「御速(おんそく)」と言って、
これができる人も含めて市指定の文化財となっています。