学校生活の様子
更新日:2025年12月19日
第五小学校児童の学校生活の様子についてお伝えします。
関連ファイル
- 令和7年12月19日(金)「今年の汚れ、今年のうちに」!(PDF:222KB)
- 令和7年12月18日(木)2学期最後の「たてわり遊び」!(PDF:241KB)
- 令和7年12月10日(水)ALTの先生とレッツ!イングリッシュ!(PDF:231KB)
- 令和7年12月9日(火)1年生 世代間交流「昔遊び」(PDF:217KB)
- 令和7年12月9日(火)ご飯と味噌汁、美味しくできました!(PDF:261KB)
- 令和7年12月8日(月)地域の方と一緒にヘルスバレーボール!(PDF:213KB)
- 令和7年12月4日(木)「国語・算数大会」目指せ!パーフェクト!(PDF:245KB)
- 令和7年12月4日(木)目指せ!なわとびマスター!(PDF:249KB)
- 令和7年12月2日(火)かけがえのない人権を大切にしよう!(PDF:246KB)
- 令和7年11月27日(木)スライド完成!さあ、発表だ!(PDF:207KB)
- 令和7年11月25日(火)1年生「園児との交流会」(PDF:223KB)
- 令和7年11月25日(火)クラスレクで仲よくなろう!(PDF:195KB)
- 令和7年11月18日(火)「小麦のひみつ」をまとめよう!(PDF:213KB)
- 令和7年11月18日(火)ぼくの、わたしの歩幅はどのくらいかな?(PDF:183KB)
- 令和7年11月17日(月)友達の作品のよさを味わおう!(PDF:185KB)
- 令和7年11月14日(金)学校公開日、お世話になりました!(PDF:218KB)
- 令和7年11月7日(金)2年生「校外学習楽しかったよ!」(PDF:214KB)
- 令和7年11月7日(金)「駅伝練習」スタート!(PDF:200KB)
- 令和7年11月6日(木)1年生「楽しかったよ!桐生が岡公園!」(PDF:202KB)
- 令和7年11月5日(水)「防犯避難訓練」を実施しました。(PDF:192KB)
- 令和7年10月31日(金)自分の考えを広げたり深めたりする児童の育成(PDF:201KB)
- 令和7年10月30日(木)さわやかジョギング、スタート!(PDF:209KB)
- 令和7年10月27日(月)「表彰朝会」を行いました!(PDF:185KB)
- 令和7年10月24日(金)図工「あったらいいな こんな町」(PDF:204KB)
- 令和7年10月23日(木)井上先生による「毛筆」の出前授業 その2(PDF:201KB)
- 令和7年10月21日(火)5年生「稲刈り体験」を行いました!(PDF:226KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集⑨(PDF:272KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集⑧(PDF:257KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集⑦(PDF:182KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集⑥(PDF:261KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集⑤(PDF:246KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集④(PDF:241KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集③(PDF:256KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集②(PDF:191KB)
- 令和7年10月18日(土)「輝く笑顔 真剣勝負で 勝利をつかめ」運動会特集①(PDF:230KB)
- 令和7年10月16日(木)「法被」を着て、ハッピー!(PDF:187KB)
- 令和7年10月14日(火)3年生「車椅子・高齢者体験」(PDF:195KB)
- 令和7年10月10日(金)「陸上記録会」自分の限界に挑戦!(PDF:263KB)
- 令和7年10月9日(木)ソーラン節練習もいよいよ佳境へ!(PDF:183KB)
- 令和7年10月9日(木)運動会本番まで残り1週間!(PDF:202KB)
- 令和7年9月25日(木)5年生「頑張るぞ!ソーラン節!」(PDF:188KB)
- 令和7年9月25日(木)運動会練習、頑張るぞ!(PDF:214KB)
- 令和7年9月24日(水)3年生「スーパーマーケット見学」に出かけてきました!(PDF:192KB)
- 令和7年9月24日(水)久しぶりの「英語村」!(PDF:223KB)
- 令和7年9月22日(月)「田んぼアート」を囲んで、ハイ!チーズ!(PDF:216KB)
- 令和7年9月18日(木)「百年小麦」ってどんなものだろう?(PDF:202KB)
- 令和7年9月18日(木)井上先生の書写の授業です!(PDF:216KB)
- 令和7年9月18日(木)2学期最初の「縦割り遊び」!(PDF:205KB)
- 令和7年9月16日(火)5年生「社会科見学」へ出かけてきました!③(PDF:205KB)
- 令和7年9月16日(火)5年生「社会科見学」へ出かけてきました!②(PDF:225KB)
- 令和7年9月16日(火)5年生「社会科見学」へ出かけてきました!①(PDF:203KB)
- 令和7年9月11日(木)「ラジオ体操講習会」を行いました!(PDF:205KB)
- 令和7年9月10日(水)3年生・5年生「移動音楽教室」に出かけてきました!(PDF:250KB)
- 令和7年9月10日(水)「陸上記録会」に向けた練習が始まりました!(PDF:198KB)
- 令和7年9月9日(火)「館林のきゅうり」について発表しました!(PDF:250KB)
- 令和7年9月4日(木)友達のよさを伝え合おう!(PDF:201KB)
- 令和7年9月3日(水)2学期の給食もおいしく食べよう!(PDF:216KB)
- 令和7年9月1日(月)2学期も元気いっぱいにがんばろう!(PDF:210KB)
- 令和7年7月18日(金)1学期よく頑張りました!よき夏休みを!(PDF:127KB)
- 令和7年7月17日(木)お楽しみ会で楽しく遊びました!(PDF:125KB)
- 令和7年7月15日(火)「館林の農業」についての出前授業(PDF:122KB)
- 令和7年7月14日(月)1学期最後のクラブ活動!(PDF:113KB)
- 令和7年7月14日(月)キュウリがこんなに大きくなりました!(PDF:138KB)
- 令和7年7月11日(金)「大掃除」一学期の汚れをピカピカに!(PDF:122KB)
- 令和7年7月10日(木)「水害避難訓練」を実施しました!(PDF:156KB)
- 令和7年7月7日(月)「ソーラン節」に向けた法被作り!(PDF:126KB)
- 令和7年7月3日(木)「情報モラル講習会」を実施しました!(PDF:150KB)
- 令和7年7月3日(木)今年度最初の「たてわり遊び」!(PDF:130KB)
- 令和7年7月1日(火)「国語・算数大会」開催!(PDF:127KB)
- 令和7年6月26日(木)「前期指導主事訪問日」開催!(PDF:136KB)
- 令和7年6月24日(火)いじめをなくそう!五小の「たいせつ」!(PDF:126KB)
- 令和7年6月19日(木)5年生「ドキドキワクワク!田植え体験!」(PDF:133KB)
- 令和7年6月17日(火)待ちに待った「水泳学習」開始!(PDF:111KB)
- 令和7年6月16日(月)2年生「トマト農家見学」へ出かけてきました!(PDF:121KB)
- 令和7年6月13日(金)「レッツ!イングリッシュ!」英語村!(PDF:135KB)
- 令和7年6月12日(木)「プール開き集会」を実施しました!(PDF:133KB)
- 令和7年6月11日(水)4年生「社会科見学」へ出かけてきました!②(PDF:118KB)
- 令和7年6月11日(水)4年生「社会科見学」へ出かけてきました!①(PDF:134KB)
- 令和7年6月6日(金)今年も「ミストシャワー」を設置しました!(PDF:138KB)
- 令和7年6月6日(金)5年生「キュウリのひみつ」をさぐれ!(PDF:129KB)
- 令和7年6月6日(金)3年生「市内史跡巡り」に出かけてきました!(PDF:134KB)
- 令和7年6月5日(木)避難訓練・引き渡し訓練を実施しました!(PDF:128KB)
- 令和7年6月5日(木)3年生「交通安全教室」を実施しました!(PDF:124KB)
- 令和7年6月5日(木)5年生「小学生歯みがき大会」実施!(PDF:123KB)
- 令和7年6月4日(水)プールもピカピカ!ピカ☆イチ!5年生!(PDF:129KB)
- 令和7年6月4日(水)1年生も新体力テスト、頑張っています!(PDF:129KB)
- 令和7年6月3日(火)目指せ!新記録!「新体力テスト」(PDF:121KB)
- 令和7年6月3日(火)「交通少年団結団式」を行いました!(PDF:123KB)
- 令和7年6月2日(月)「救急救命講習会」を実施しました。(PDF:127KB)
- 令和7年5月28日(水)ドキドキ!ワクワク!初めての調理実習!(PDF:114KB)
- 令和7年5月27日(火)絵の具・ニスを塗って、きれいに仕上げよう!(PDF:128KB)
- 令和7年5月21日(火)休み時間も元気いっぱい!五小っ子!(PDF:121KB)
- 令和7年5月20日(月)図工「糸のこぎり」にチャレンジ!(PDF:121KB)
- 令和7年5月16日(木)「青少年赤十字」登録式を行いました!(PDF:122KB)
- 令和7年5月16日(木)「緑の少年団」結団式を行いました!(PDF:121KB)
- 令和7年5月8日(木)1年生「学校たんけん」へ出発!(PDF:119KB)
- 令和7年5月8日(木)楽しかったよ!林間学校!④ ~ピザ作り~(PDF:122KB)
- 令和7年5月7日(水)楽しかったよ!林間学校!③ ~キャンプファイヤー~(PDF:116KB)
- 令和7年5月7日(水)楽しかったよ!林間学校!② ~ポスト探しゲーム~(PDF:120KB)
- 令和7年5月7日(水)楽しかったよ!林間学校!① ~施設到着~(PDF:127KB)
- 令和7年5月1日(木)元気いっぱい!「五小サーキット」!(PDF:120KB)
- 令和7年4月28日(月)「1㎥」ってどのくらいの大きさ?(PDF:128KB)
- 令和7年4月22日(水)読み聞かせボランティア、今年もお世話になります!(PDF:124KB)
- 令和7年4月17日(木)ドキドキ!5年生最初の毛筆!(PDF:124KB)
- 令和7年4月16日(水)今年度最初の一斉下校!(PDF:118KB)
- 令和7年4月11日(金)地球儀を使って、世界の国々を調べよう!(PDF:121KB)
- 令和7年4月11日(金)「1年生を迎える会」を行いました!(PDF:124KB)
- 令和7年4月8日(火)ピカ☆イチ!5年生!五小を明るく照らそう!(PDF:114KB)
- 令和7年4月7日(月)第五小学校へようこそ!ピカピカの1年生!(PDF:138KB)
- 令和7年4月7日(月)令和7年度スタート!新しい1年の始まりです!(PDF:145KB)

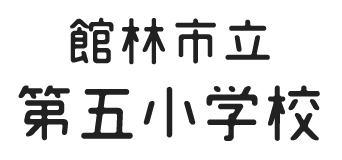
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。