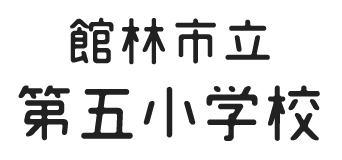普済寺の銅鐘
更新日:2021年3月24日
五小近くにある普済寺の銅鐘は、慶安2年(1649)、下野国天命(現在の栃木県佐野市)の鋳物師がつくったもので、全体が細長く古い形を残し、江戸時代の鐘の特色をよく表しています。
口径69センチメートル、胴の高さ99センチメートル、全長1.26メートルになります。鐘にほり付けられた文のうち、「羽継」とあるのは、現在の「羽附町」の昔の名前です。
昭和50年3月、市の重要文化財に指定されています。
(この文章は「館林かるた」の読み札を一部書き換えたものです。)

「館林かるた」の絵札が貼られた石柱がありますが、こちらは現役の鐘です。

こちらが館林の宝、本物の銅鐘です。今は青緑色になっていますが、つきられた当時は新しい10円玉のような色で輝いていたんでしょうね。
普済寺はしだれ桜でも有名。毎年とても見事な桜がさきます。個人的にはしだれ桜ははなれて見るよりすぐ下に入って見上げる方が良いと思いますが、みなさんはいかがですか?
このお寺にまつわるエピソード
その1 館林城を守るために引っ越しをした!
この寺は、1523年、羽附村の町谷(今の羽附旭町の一部)に建てられましたが、その二年後、城沼の東岸「篠が崎【ささがさき】」(今のつつじ町の一部)に移されました。そして、1555年までには現在の場所に引っ越しました。篠が崎に引っ越した理由は分かりませんが、現在地に引っ越したのは、当時日本にやってきた新兵器「火縄銃」と関係があるようです。
当時の鉄砲の射程距離は200メートル程度といわれ、それだと、篠が崎に敵が来ると、そこから城内まで、鉄砲玉を打ち込むことができてしまうと言うので、ここに出城を築く必要があったようです。
その2 和尚さんが教科書に出てくる有名人と仲良し!
五代目の和尚さんは、上杉謙信さんの弟と言われています。また、徳川家康さんと幼友達で、家康さんが今川さんの人質になっていたとき、そこから脱出するための手助けをしたと言われています。
ある意味、歴史を動かしたすごい人ですね。だから、1591年、家康さんは和尚さんにそのときのお礼として、板倉町の土地の一部をお寺の領地としてプレゼントしてくれたそうです。