家屋に対する課税
更新日:2024年4月1日
課税対象になる家屋
固定資産税及び都市計画税の課税対象になる家屋とは、以下の要件を満たしているものです。
- (外気分断性)屋根及び3方向以上の壁があり、扉やシャッターなどの建具に囲まれていて、風雨をしのげるものであること
- (土地定着性)コンクリートの基礎などで土地に定着しており、容易に移動できないものであること
- (用途性)居住、作業、貯蔵など、その目的とする用途に利用できる状態にあること
課税対象(例)サンルーム、車庫、物置(連続してブロックなどが施工されているもの)、ガラスハウス、テント倉庫
課税対象外(例)テラス、ウッドデッキ、カーポート、物置(点在するブロックの上に置いてあるもの)
家屋調査のお願い
新築又は増築された家屋は、完成の翌年度から固定資産税(都市計画税)が課税となります。
課税にあたっては、固定資産税評価額を算出するため、地方税法に基づき、調査員(税務課家屋担当職員)が訪問して家屋調査を行います。
家屋調査時には、家屋の外部や内部の各部屋(クローゼット等の収納を含む)を調査させていただくため、施主又はご家族のかたなどの立ち会いをお願いします。調査にかかる時間は、税金の説明を含めて1時間ほどです。
なお、家屋調査時には次の物をご用意ください。
〔家屋調査時に必要な物〕
- 建築確認申請書
- 長期優良住宅に該当する場合は、認定通知書の写し
家屋を新増築、取り壊し、用途変更したときは
家屋を新増築、取り壊し、又は用途変更した場合には申告が必要です。詳しくは、住宅用地に関する申告をご覧ください。
未登記家屋の名義変更をしたいときは
売買や相続などがあった場合、登記されている家屋だけではなく、未登記家屋の名義変更についてもお忘れのないようご確認ください。
未登記家屋の名義変更をしたい場合は、申請書の提出が必要です。詳しくは、未登記家屋の名義変更をご覧ください。
評価のしくみ
家屋調査の結果から、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、「再建築価格方式」により評価額を算出します。
新築家屋の評価について
家屋調査により確認した家屋の屋根、外壁、基礎、天井、内壁、床、給排水設備、電気設備等を「固定資産評価基準」にあてはめて再建築価格を算定し、経年減点補正率を乗じることで評価額を算定します。
〔新築家屋の計算式〕 評価額=再建築価格×経年減点補正率
注:再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費
注:経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をあらわしたもの
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価について
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
〔在来家屋分の計算式〕 評価額=再建築価格×経年減点補正率
注:在来家屋分の計算式における再建築価格は、「基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率」で算出します。再建築費評点補正率とは、前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率で、令和6年基準では木造家屋は1.11、非木造家屋は1.07です
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。
なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。
税額の計算方法
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
課税標準額(価格)×税率=税額
減額措置について
以下の要件に該当する場合、申告書の提出により、一定期間固定資産税の減額措置を受けることができます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
対象要件
- 専用住宅や併用住宅、共同住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては一世帯あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額範囲
住居として用いられている部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税額を2分の1減額
注:併用住宅における店舗部分・事務所部分などは対象外
注:住居部分の床面積が120平方メートルを超えるものは、 120平方メートル分までが対象
減額期間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分
- 一般の住宅(上記以外の住宅):新築後3年度分
必要な書類
長期優良住宅の新築に伴う固定資産税の減額措置
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことで、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であり、同法の施行日(平成21年6月4日)から新築された住宅が該当します。
長期優良住宅を新築し、要件に該当する場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。
注:長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます
対象要件
- 長期優良住宅の普及と促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
- 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅であること
- 延床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合、延床面積が40平方メートル)以上280平方メートル以下(併用住宅の場合、住宅部分の面積が全体面積の2分の1以上)であること
- 新築した翌年の1月31日までに必要書類を添付して申告すること
減額範囲
- 中高層耐火住宅:新築された家屋1戸につき120平方メートル分までの固定資産税額を2分の1減額
- 一般の住宅:新築された家屋1戸につき120平方メートル分までの固定資産税額を2分の1減額
減額期間
- 中高層耐火住宅:新築後7年度分
- 一般の住宅:新築後5年度分
必要な書類
- 認定長期優良住宅減額申告書
- 長期優良住宅認定通知書など、長期優良住宅を証する書類の写し
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置
新築された住宅については、一定の要件に該当する場合、固定資産税が一定期間減額されます。
対象要件
- 令和7年3月31日までに新築された住宅であること
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅として登録されていること
- 戸数が10戸以上であること
- 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下であること
- 国から建築費補助を受けていること
- 主体構造部が耐火構造であること又は準耐火構造であること
- 新築した翌年の1月31日までに必要書類を添付して申告すること
減額範囲
- 1戸当たり120平方メートル分までの固定資産税額を3分の2減額
減額期間
- 新築の翌年度から5年度分
必要な書類
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類
- 国の補助を受けている旨を証する書類(写し)
- 主要構造部が耐火構造の建築物又は準耐火構造の建築物であることを証する書類(建築確認申請書の写し)
- 家屋平面図
耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
耐震改修工事を行い、要件に該当する場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。
耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額
対象要件
- 専用住宅や併用住宅、共同住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
- 昭和57年1月1日以前に建てられたものであること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 耐震改修工事の費用が50万円以上であること(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は30万円以上)
- 耐震改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告すること
減額範囲
住居として用いられている部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税額を2分の1減額(長期優良住宅の場合は3分の2減額)
注:併用住宅における店舗部分・事務所部分などは対象外
注:住居部分の床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分が対象
減額期間
工事完了が平成18年から平成21年:工事完了後3年度分
工事完了が平成22年から平成24年:工事完了後2年度分
工事完了が平成25年から令和8年3月31日:工事完了後1年度分
注:建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物の場合は、改修後2年間
必要な書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証する書面
- 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書
- 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額
対象要件
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋であること
- 平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に国の補助を受けて耐震改修工事をした家屋であること
- 住宅においては住宅耐震改修特例の対象部分を除いた部分
- 耐震改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告すること
減額範囲
耐震改修工事が完了した家屋の固定資産税額を2分の1減額
注:ただし、減額の上限は補助対象工事費の2.5%
減額期間
工事完了後2年度分
必要な書類
- 耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に係る固定資産税減額申告書
- 地方税法施行規則附則第7条第13項に規定する補助金確定通知書の写し
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条又は同法附則第3条第1項の規定による耐震診断の報告の写し
- 地方税法施行規則附則第7条第14項の規定に基づく証明書
省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
省エネ改修工事を行い、要件に該当する場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。
対象要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。また、併用住宅は居住用部分の割合が2分の1以上)であること
- 平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に熱損失防止改修(省エネ改修)工事(窓の断熱改修や、窓の断熱改修と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修)を行い、当該工事に要する費用が国、又は地方公共団体からの補助金を除き、60万円以上であること
- 改修後、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 新築家屋に対する軽減及び耐震改修に伴う軽減が適用されていないこと
- 省エネ改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告すること
減額範囲
省エネ改修工事が完了した家屋の固定資産税額を3分の1減額(長期優良住宅の場合は3分の2減額)
注:1戸の住宅につき120平方メートルまでを限度
減額期間
改修後翌年度分
必要な書類
- 熱損失防止改修(省エネ改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 省エネ改修に要した費用を証する領収書
- 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
バリアフリー改修工事を行い、要件に該当する場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。
対象要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。また、併用住宅は居住用部分の割合が2分の1以上)であること
- 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事(廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化)を行い、国、又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金額が50万円以上であること
- 改修後、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 65歳以上の人、要介護認定又は要支援認定を受けている人、又は障害者の人のいずれかが居住していること
- 新築家屋に対する軽減及び耐震改修に伴う軽減が適用されていないこと
- バリアフリー改修工事完了後3か月以内に必要書類を添付して申告すること
減額範囲
バリアフリー改修工事が完了した家屋の固定資産税額を3分の1減額
注:1戸の住宅につき100平方メートルまでを限度
減額期間
改修後翌年度分
必要な書類
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 65歳以上の人の住民票、介護保険者証、又は障害者手帳のいずれかの写し
- バリアフリー改修工事に係る明細書(工事の内容・費用が確認でき、工事箇所の工事前後の写真があること)、又は増改築等工事証明書
- バリアフリー改修工事に要した費用を証する領収書

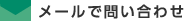
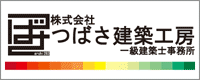

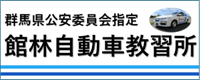
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。